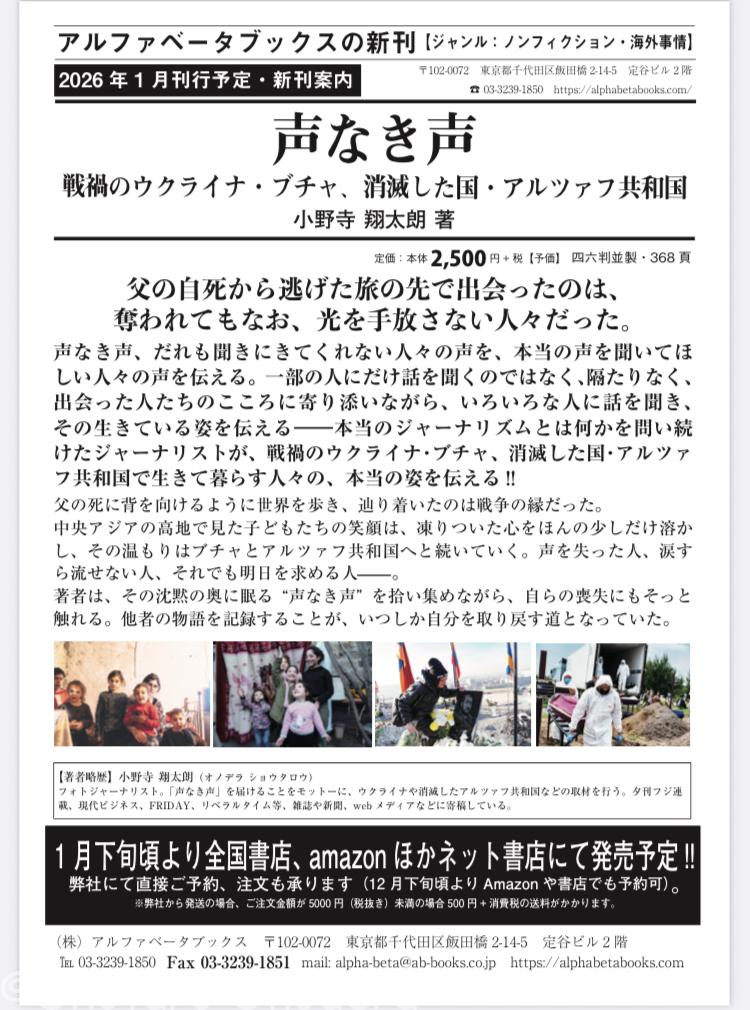「まずは、自分のしてきたことの重さをきちんと認識し、お父さんに対して、そして私たちに対して心からの謝罪をしてほしいです。
お父さんが亡くなった日、私は現場にいました。
あの時の苦しそうな表情、もう生きていないと一瞬でわかる体の冷たさや硬さは、今でも頭から離れません。死の直前までどれだけ辛かったか、その表情がすべてを物語っていました」–妹の言葉
わたしは機能不全家族で生まれた。父もそうだ、そして最終的に父は首を吊って亡くなった。そして、それが原因でわたしは弟と喧嘩別れし、妹とは会わなくなった。後に父が建てた黄色い家は売られた、と噂で聞いた。わたしは家族と帰る家を失った。そのことは、わたしが取材活動を始めたことに大きく関係しているのだと思う。
あの取材の日々、一体わたしはなにを求めていたのだろう。

父の自死から逃げた旅の先で出会ったのは、
戦争に全てを奪われてもなお、光を手放さない人々だった。
父の死に背を向けるように世界を歩き、
辿り着いたのは戦争の縁だった。
中央アジアの高地で見た子どもたちの笑顔は、
凍りついた心をほんの少しだけ溶かし、
その温もりはブチャとアルツァフ共和国へと続いていく。
声を失った人、涙すら流せない人、
それでも明日を求める人——。
著者は、その沈黙の奥に眠る“声なき声”を拾い集めながら、
自らの喪失にもそっと触れる。
他者の物語を記録することが、
いつしか自分を取り戻す道となっていた。
父は、自ら死を選んだ。
そして私は、戦場へ向かった。
そんなわたしが、虐殺の街ブチャで
出会ったのは、ある一人の女性だった—